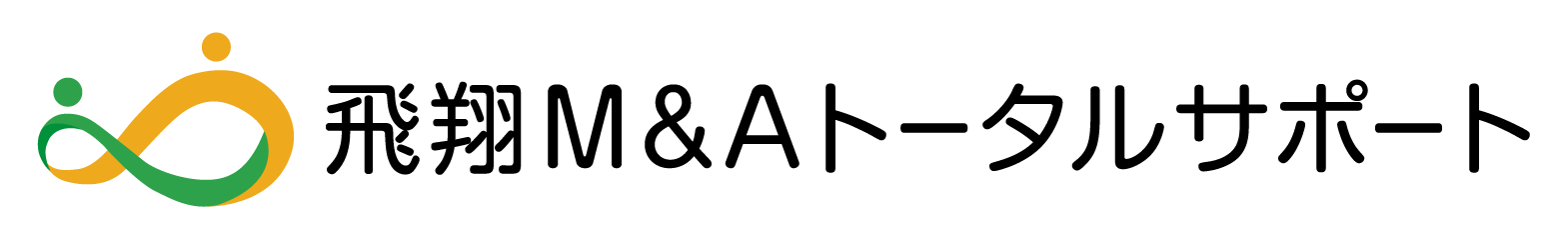M&Aでは、売手と買手の間で大きく分けて3段階の合意書面が交わされます。
第1段階は、クローズな情報を開示するにあたって秘密保持に関する事項を定めた秘密保持契約書(CA又はNDAと呼ばれるもの)です。
第2段階は、秘密情報の提供を受けてM&Aを前向きに進めることになった場合の基本合意書です。デューディリジェンス(DD)の前に締結されるのが一般的です。
第3段階は、そのデューディリジェンスを経て締結される最終契約書(株式譲渡形式なら株式譲渡契約書、事業譲渡形式なら事業譲渡契約書)です。
これらのうち、秘密保持契約書は秘密保持に関する事項を定める目的、最終契約書はクロージング内容を定める目的ということで、締結の目的が分かり易いものです。
では、基本合意書はどのような目的のために結ぶのでしょうか。この点は、売手と買手とで視点が異なりますので、順に見て行きます。
まず、売手としては、オープン情報に加えて秘密保持契約締結後にクローズな情報も提供し、双方の希望条件等もすり合わせて、概ねM&Aの条件が煮詰まった段階で基本合意書を締結することになります。
そのため、基本合意書締結後になされるデューディリジェンスで余程重大な事案が発見されない限り、条件を大幅に変更することなく買って欲しいというのが、売手の希望になります。デューディリジェンスは、対象企業又は対象事業に問題点がないかを確認する手続ですので、問題点、すなわち減額要素を見付ける手続とえいます。
そのため、デューディリジェンス前にできるだけ厳格な基本合意書を作成して、上記の通り余程重大な問題点が発見されない限り金額その他の条件面を変えられないようにしておくために基本合意書を締結することになります。
そこで、売手が基本合意書に期待する目的は、デューディリジェンス前にM&A条件を可能な限り固定するというものになります。それ故に、売手にとって望ましい基本合意書は、最終契約に相当近いものであり、細かな定めを置いたものとなります。
次に、買手の視点で見てみます。
買手としては、デューディリジェンス前ですので、どのような問題点があるか確認できていない段階ですので、条件を変更できないような細かな定めを置きたくないところです。
デューディリジェンスの結果、リスクを排除する必要性が高ければ株式譲渡形式から事業譲渡形式に変更するなどスキーム変更の可能性もありますのでM&Aの形式自体も固定せず、金額その他の条件面も明記しないのがベストであり、仮に明記するとしても現状の予定額として変更が容易な形式にしておくのが望ましいでしょう。
そのため、一般的には、買手は緩やかな建付けの基本合意書を好みます。但し、買手は基本合意書締結の後に費用をかけてデューディリジェンスを実行することになりますので、一定の期間の独占交渉権確保だけは必須のものとして要求すべきでしょう。その理由は、費用をかけて調査している途中で売手が第三者との間でM&Aをしてしまうという事態を避けるためです。
買手が基本合意書を締結する目的は、独占交渉権確保が中心であり、他の部分は基本合意書を締結した後に行うデューディリジェンスの結果に応じて柔軟に対応できるように細かく定めない方が良いということになります。
このように基本合意書を締結する目的が売手・買手の双方の立場によって異なることを踏まえますと、どの程度まで規定する方が良いのか、文言をどうすべきかといった点は繊細な問題となります。
また、買手が確保したい独占交渉権についても、売手としては長過ぎると足枷になるので、期間を限定するなど調整の必要があります。
こうした点を踏まえ、最終契約書は当然のことながら、基本合意書についてもM&Aに精通した弁護士のリーガルチェックは必須と考えます。
なお、上場会社が当事者となるM&Aにおいて、規模その他の要素にもよりますが、適時開示が必要となる場合には、基本合意書を締結してしまうと、その時点で情報開示をする必要が生じることになりますので、状況により基本合意書の締結を省略する場合があります。
他にも当事者間の関係性等により基本合意書の締結が省略される場合は少なからずありますが、こうした省略をする場合には、基本合意書を締結して確保しようとした目的が締結しない中でどのような方法でどの程度確保できるのかといった点も十分に検討して対応することが必要となります。